パターンを見る–
04パターンを見る
我々は原始より自然界の事象の中にパターンを見出し、
それらを効率良く理解するための手段として、
またはそれらを想起させる意匠として利用してきた。
現代においても交通渋滞の緩和や気象の予報、集団心理の考察など、
パターン化することに拠って問題解決の糸口の
創出となることは多々見受けられる。
何層にも折り重なった情報の層から特定の条件で
断片をピックアップし、より次元の低いメディアに投影する。
複雑な状態は平面的にテクスチャ化される。
情報をテクスチャとして見ることとは何を意味するか。
ある特定の強度のみが表象としての情報を浮き上がらせ、
その他は情報を持たない、つまり0の階調として扱われる。
これは一種の単純化、定義付け、特定範囲内の統治であり、
言語である。
同様のものを絵画に見て取る、という行為は可能だろうか。
絵画は一定の規則のもとに集められた色彩の集合である。
特定の言語で語られるハイコンテクストな土壌は、
まさしく自然界のマクロな活動形態と
トポロジーを成しているように思われる。
我々は気候を読むように、絵画を読むように、
パターンを見る。
パターンは理解を促進し、複雑を可能にする。
パターンはまた、新たなパターンを生む。
(Tomonori Koyama、2010)
傍観するということ、Trans–Fluid–
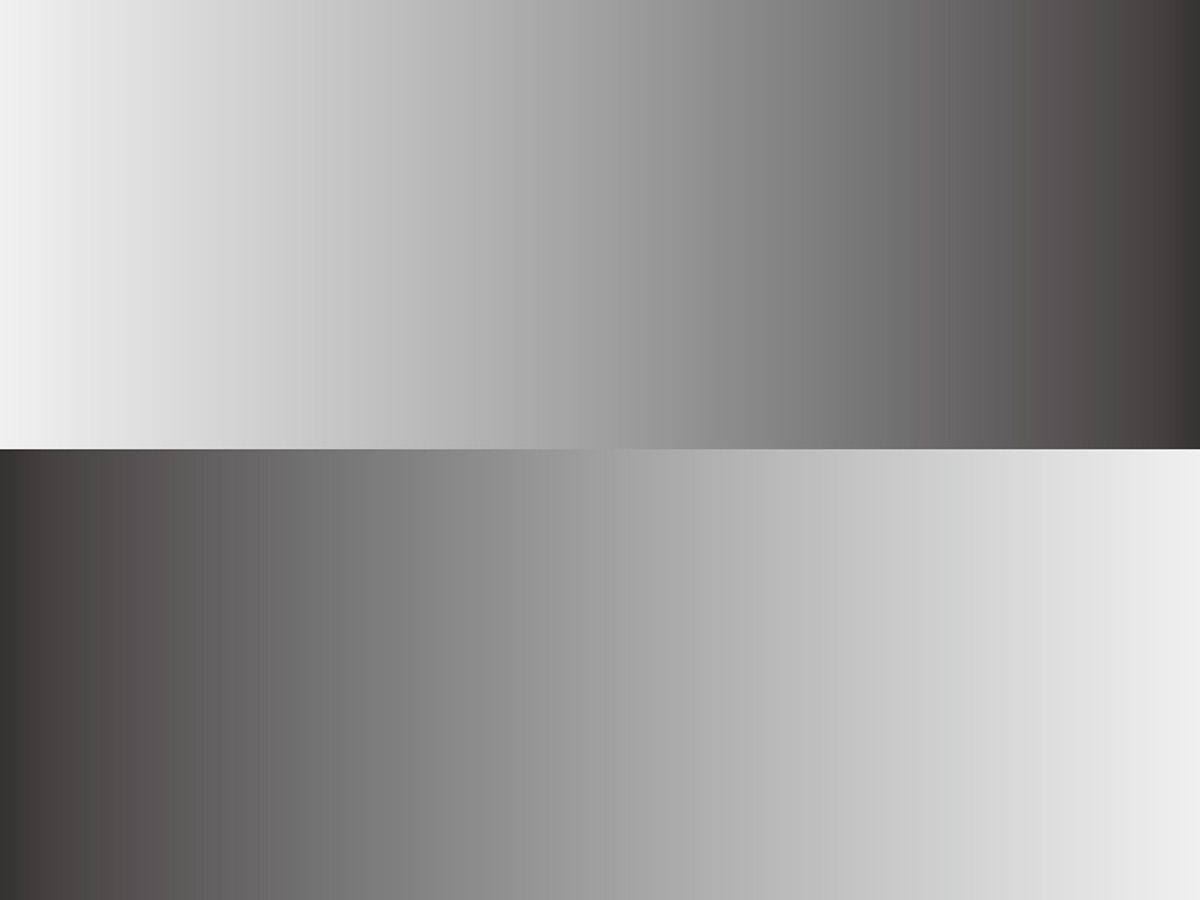
02傍観するということ、Trans–Fluid
光源から放たれる一過の光を見る。
光はどこまでを光と呼ぶだろうか。
光が無くなれば、
光によって見えたものは、見えなくなり、
光によって見えなかったものは、見えるようになる。
我々は定められた物事の内側だけを漂っているわけではない。
物事の定まらない中間地点に多くの情報を見出し、
言語化しようとする。
例えば、
川が合流する地点、
動物の鳴き声、
混血の生物、
機能を失った道具。
それらの連続が、それらの領域を成長させ、
揺るぎない一筋の流れを生み出し、また分裂していく。
発展とは認識を発端とし、進歩とは過去への賛辞と退化の連続を伴う。
我々はこうして多くのことを再生産し、そこに価値付けをし、
ときには熱意を向け、消費する。
これらを傍観するということ。
変容の総体に意識を向けながら、
流れゆくそのものを、冷静に見つめる。
あたかも天文学者かのように、
見えない事実を生み出すかのように。
生きることとは、見ることだ。
光が見えなくなるまで、自ら光としてあることだ。
その変遷の傍観者は無二の価値を見いだせるだろうか。
しかし、光によって映しだされ暴かれた対象は、
即様に視覚の非対象となる。
(Tomonori Koyama、2010)
空虚な眼差し–
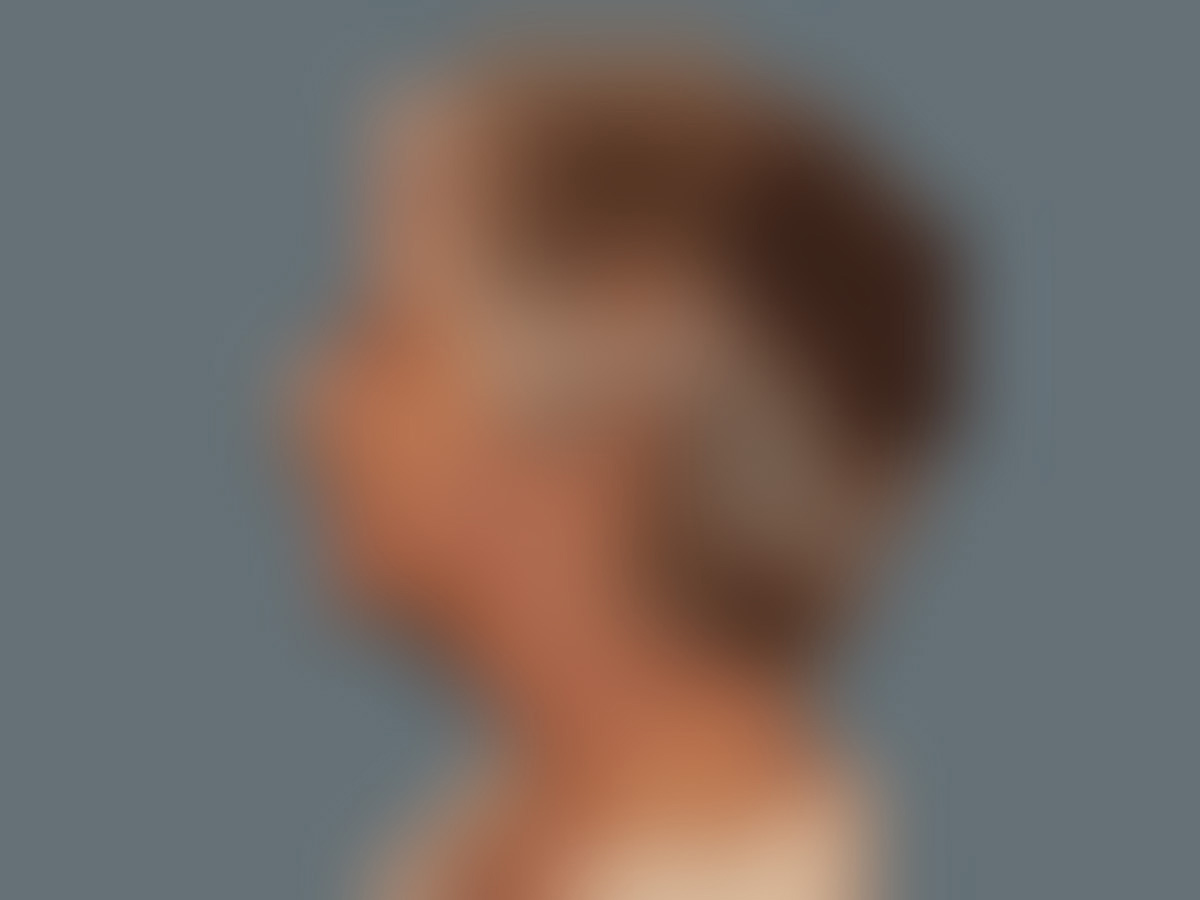
03空虚な眼差し
横顔について。
他者による非情な客体化により、
「私」は物事の対峙から脱却させられる。
我々はより次元の低い、つまり現実からそれを模倣したものや、
もしくはそれを転写したスクリーン達と接触する機会を増やすことで、
より高次元へコミュニケーションを強めていく。
人を横から見たとき、「私」は何と対峙していたのだろうか。
もはや対象さえもなく、
不在と格闘しているかのように見えるその顔は
対象を自己の中に取り込み、現実で補完していく。
横顔、–profile。
横顔は、それを見るものとのコミュニケーションの
切断を示唆しているようであるが、
そこに空虚な何かとコミュニケイトする眼差しを見て取れる。
仮想的な無限遠にピントが合った視点は、
フィジカルな体験との比較を無意味にし、
まるで菩薩のように佇む。
(Tomonori Koyama、2011)
*画像は初期AI技術において自動生成された人物の横顔にピントを外したもの。
「手」にとるすべもなく–
[ + ]
[ – ]
figure
01「手」にとるすべもなく
物質としての物の総量は日々増加していく。
同時に、私達が気付かぬうちに消えゆく物もある。
物が細分化され、増殖し、有り様も複雑になれば、
その多様性は一意の豊かさを形成する。
我々の目に入るものは、物事の全体からするとほんの一部に過ぎない。
細かな生活の変化を宇宙から観察し、見てとるような行為を
日常的に行うことは難しい。
物事の総体はそれらを構成する細部の集合である。
人間の各々の細胞が分子レベルで激しく運動をしても
人間という総体は固定されているように、
物事も細かな事象の集合を平均し、
平衡状態を一定のルールで維持する。
つまり、多様であるための特異性も一種の平衡状態の構成要素であり、
動的にルールを持つ環境の中では必要不可欠なのだ。
性別、宗教、人種。
人間の決めた規則や倫理にそって認識するその概念を超えて
自然や宇宙のより高度な秩序に任せる、という状態を認識すること。
それ以上でもなくそれ以下でもないこと。
気付かぬうちに変化していることさえも、
変容する個体としては変わっていないように、
我々の認識する眼はすべての認識を不可能にする。
(Tomonori Koyama、2006)
