time & river–

今から800年ほど前に、存在は時間そのものであるという結論に達した人物がいた。道元である。西洋で時間が哲学される随分前になる。この世のすべてはおおよそ実態がなくバーチャルである、といったのは釈迦やナーガールジュナだったが、存在が実態がなく「現象」であるからこそ、そこに確かな「有」を求めるのが人間の性なのだろう。
私はバーチャルなこの世界の現実においてますます「日常」が重要だと考えている。日常とは何なのか、なぜ日常かを話そうとすると膨大な時間論やベルクソンの考え、様々な存在論を経由する必要があるので簡単に説明は難しい。
ただ、かの道元においても「有時」なる概念にて、生きている24時の生活そのものに習うべしとあった。つまり一切の日常の現象=存在が、その本体である時の働きによって現れている姿だということである。
時の働き、現れが「有」である。しかし時間そのものがある/なしで言えば限りなく「ない」。本質的には「ない」ものが現れとして現成しているのが「有」であるとすると、それは仮象になる。ヘーゲルは、わずかであるが表面に本質が現れたものを仮象と呼び、自己が他者の形で現れたものとした。
「有時」にて道元は、有時(存在と時)が本来の自己であるという。それは「ない」ものに支えられ仮に現れる。だからバーチャルではあるのだが、限りなく真を求め続ける運動でもある。
そしてこの結論じみたものもまた仮であり、何か大きな流れの中に漂う細かな粒子のようなものに過ぎないのだろう。
届かぬ場所–
沈黙の中に言葉が立ち現れれば、それはもう詩となっている、とマラルメはいう。マラルメにおける詩は言葉を超えた無に至る旅であった。
ただし完全な沈黙は何も分節しない。禅において、また公案では絶対無分節と経験的分節の同時現成が核であり、この経験的世界(ロゴス)の否定、つまり論理が記録する文化的表象としてのリアリティを剥奪するのが第一に求められる。
マラルメは意味それ自体ではなく、意味の余韻を詩の境地とした。それは言語が立ち現れる前の純粋有を無媒介的に何とか言語で言い表そうとする矛盾の発露でもある。
「言葉が届かないところに詩がある」
このマラルメの言葉を拡張してみる。
「意識が届かないところに存在がある」
「存在」は「世界」に変えても良いだろう。
マラルメは今や言葉を発することができず、さぞ幸せなのだろうか。
如去–

如来を意味するサンスクリット語のTathāgataには、如に行った(如去)と如から来た(如来)の両義が含まれている。つまり現象として現れてはいるが、流転に巻き込まれない真理に即した存在ということになっている。
人は両義的なものや大いなる矛盾を超越的なものとして作り出すが、それらは人そのもののアプリオリとして、予め特別でない性質として備わっているものだということを再認識する必要がある。
人が作り出す概念はどこかしら人間の内的な存在事項として見出されるものであり、人が人である限りそれらは予定されている。人が媒介しない契機はそもそも存在すら想像され得ないのだ。
itself–
私たちが人間以外を深く思うとき、それは「そのようにある」ことでは決してなく、ただ美的な相似をなぞらえているだけなのである。
成就–
私たちは非連続の存在であり、理解できない運命の中で孤独に死んでいく個体であるが、しかし失われた連続性へのノスタルジーをもっているのだ。
ジョルジュ・バタイユ
事事無礙–

華厳思想を学んでいると、理事無礙――事事無礙における理や事の生成過程やその関係性とアルフレッド・ノース・ホワイトヘッドの活動的存在、活動的生起の生成と価値化を比較したくなる。
華厳においては絶対的無分節、つまり空である「理」がひとつのものとして自己分節的に現象し、我々が経験的世界と呼ぶような森羅万象の世界「事」が生起する。つまり「理」は「事」に侵入して「事」そのものとなり、「事」は「理」を体現し、結局「理」そのものをあらわしている。
そして事と事が相互に関係して一つに融け合い、一つの事のなかに他の無数の事がイメージとして映り込むのが事事無礙である。
ホワイトヘッドでは活動的存在は唯一無二でありそこに一切の価値があるとされ、各々が主体となった連関世界において非連続の連続というあり方で生成消滅している。そしてその活動的存在は瞬く間に他の対象となり過去化しながら延長連続体へと埋没する。
双方において多即一、一即多であり、ゼロは無限性の地平へと投企される。
これら時間的契機における刹那滅や存在解体と再生成において、「生きた現在」をどのように矛盾から開放するかということが個人的思考の主題になりつつある。しかしそういったことさえも、断片的に分解と生成を繰り返した後の空虚な実感としてしか連続しないのかもしれないと<いま・ここ>で考えている自分がいる…
抽象絵画と矛盾–
この今の時代に抽象絵画を描いているものを見るたびに思うものがある。
ロザリンド・クラウスがかつてアド・ラインハート等についての批評において、抽象が持つパラダイムの再帰性について書いていた。
抽象芸術の諸パラダイムに組み込まれた両義性―純粋な観念と完全な物質性という宙吊り―はその内的矛盾によって特徴付けられるという。
形態を再発明しようとする欲求に原動力を与えるのがその矛盾ならば、それが事実として反復であることを否定しようと油を注ぐのもその矛盾なのだと。
レヴィ=ストロースの指摘、神話それ自体は繰り返し舞い戻ってくるばかりの根深い文化的矛盾への反応だという言説を引き合いに、これらの回帰の形式/反復強迫が生み出すものは次のようなことだ。
1. 抽象のパラダイムが所与の芸術家の実践の中でシリーズ化の手段となる。つまり、わずかな差を生じつつ複製を延々と連鎖させ同一フォーマットを繰り返す。
2. その抽象が完全に単純な形態であるにもかかわらず内的矛盾の感覚を生み出すという事実を強調する。
オリジナリティという虚構の維持のための自己―欺瞞性がここにあり、観るものを把捉を絶えずかわすのだ。
ヘラクレイトスから–
「対峙するものが和合するものであり、もろもろの異なったものどもから最も美しい調和が生ずる」とヘラクレイトスが言うように、自然と人は相反するものとして和合を目指すがゆえにその過程が美しい調和として「人には」認識されうる。
人は人の相関の内/外を意識的に選択するが、それさえも人の思惟だということへ取り込まれるこの差異吸収のシステムを否定した際、まったくもって「それらしくない」文脈を、「それらしい」ものとして受け入れることへ人は到達できるのだろうか。
過程と真理–

アラン・バディウは言う。
芸術における真理は、真理と厳密に共存在的であり、科学や愛、政治の真理へと還元不可能である、と。
芸術は真理を受け入れる能力がないとする教育主義的発想や、真理を受け入れキリスト教的な図式で無限なる力を受肉させるとするロマン主義、はたまた治癒的なカタルシスに限定することで真理と無縁にさせる古典主義のどれもが間違いであり、芸術が持つ効果こそが哲学的対象となる。そして作品群が真理の過程のまったく新たな現実存在を課す場合、それは「非美学」として哲学的に語られ得る。
真理は出来事――状況に対して過剰なもの、によって始められた芸術的「過程」であり、この過程を構成するのは様々な作品にほかならないのだ、という。
ここでの作品とはある真理の局所的審級、識別点となる。これはエルンスト・ゴンブリッジが、芸術とはその時代における行為の連続性であると見たことと重なる。またホワイトヘッド的に全ての事物が魅了し合いほのめかされていることによって立ち上がる関係性の生成プロセス=抱握が、何よりも先回りしていることから第一哲学的なものが美学とされることにも繋がる。
なので芸術家と名乗ろう者たちは、諸真理の探究結果としての作品が新たな存在の予期として機能することを期待しつつも、単一の真理的固有性を手放し、非美学的な思弁的プロセスと無限性へのコスモロジーとしての過程へと向かわなければいけない。
この双方向的な矛盾律の包まれが、苦悩/原初的な生の喜びという対峙と相似を成し、大河への流れ=プロセスへと私たちをいざなうのである。
知ることで–
私たちは、「誰かが考えていること」を知ることができて、そのことによって「私が考えていること」を知る。
by new relation–

表現と批評、またそれらの言説というのはダブルコンティンジェンシーな側面を見ることがある。相手とする対象の出方次第で、またその可能性を十分に含ませていることこそによって、意味を回収可能とする他者依存性を肯定する。
量子物理の世界にも不確定性原理というものがある。相手に今の気持ちを聞こうとすると、その行為によってその人の本当の気持ちが見えなくなる、みたいなことだ。
表現の意味が、解答のある問題に対応していないこととは別に、こういったコミュニケーションの相互関連の不明確さがまた表現の意味性を理解の奥底に追いやる。
私たちは触れられない空気と同居しながら、同時にその空気をも吸っている――そういったことをしている。無自覚的に。
知覚–
写真を知覚するとき、写真の対象の正面は、
その写真から想起されるものの反事実的な知覚を含むことを余儀なくされている。
写真が記録以上を望むとき、写真は無限の想起の連続からその正面性を無意味にし、情報のレトリックの海で、誰が最も混じり気のない原料をすくい上げられるかというゲームをしている。
人は写真に何か大きな期待をしすぎたのかもしれない、と思うことがある。
基準–
世に価値の基準は無限にある。多くの価値の中の1つを唯一の価値だと信じてしまえば、それは劣等感に繋がる。
よって価値基準を増やすとともに、すべて等しくそれほど価値はないと考えることも時には重要だと思っている。
意識–
意識とは何だろうか。
ある説では人の意識は3,000年前に発出したとされ、言語における比喩や書き文字がそれを可能にした。内的な思考言語で時間を空間化したことで、時間の向きが意識を生んだようだ。
それまではいわば自己意識がなく、右脳(神のお告げという幻聴)に従う「二分心」だったという(そしてこれは統合失調症の状態と近いらしい)。
我々は日々毎秒何百万ビットの無意識を生成し、それを元に何かしらの判断をするのだが、トール・ノーレットランダーシュやベンジャミン・リベットによると、これら膨大な情報が無意識の経験パターンで凝縮され、数十ビットの意識として処理される。
つまり私たちの言動は起こる0.5秒前にアルゴリズム的に決定されている。そしてそれを実行に移す寸前――0.1秒前に踏みとどまる自由しか与えられていない。
無意識の膨大な情報は捨て去られるにも関わらず、私たちは自分で何かを選んだと「思わされている」。
これが神経生理学上での事実だ。
一方、スピノザにおいては人間には自由意志はないと言う。全ての個物は神を原因としているからだそうだ。
意識は生まれた。しかし幻想だった。これが言語の弊害なのだろうか。
この「今」を「ある」としているのは何なのだろうか。
言語の限界を越えて–
言葉は言葉でしか表されない。言葉は最小単位である。
言葉を集めた言語は誰のものでもない。誰のものでもあるが他者でしかない。
他者は永遠にわかり得ることはない。そして自分さえも他者にとっての他者である。
もし完全な「倫理」があるとすると、それは私の固執を超越したところをもって、あらゆる知識や経験に左右されない絶対的な位相としての「他者」を尊重することから始まる。
これは言葉を習得することと似ている。
圧倒的に異なるものは、まずは受け入れるしかないのだ。
word–

言葉とは呪いのようなものだと思うときがある。
多くの感情をひとつの言葉で表現したとき、言葉で表されずこぼれ落ちる感情がある。つまりそこには必然的に嘘が生まれる。
言語化するということは言葉の持つ力を放つことであり、ときにはそれが自分に災いをもたらし、ときには神が宿ったりする。
言葉に真実はない。どんなに的確な言葉であっても、都合よく解釈されうる。
「そらみつ大和の国は 皇神のいつくしき国 言霊の幸はふ国」
山上憶良
存在論–

AIによるクローン化が目の前に迫っている。メイヤスーの思弁的実在論、マルクス・ガブリエルの新しい実在論、グレアム・ハーマンのオブジェクト指向存在論など人は実在に夢中で、私たちの存在の確かさそのものを確かめようとする。ここで井筒俊彦という脅威の偉人に目を向けたい。
井筒は「花は存在している」の主語は「存在」だと言う。つまり言い換えると「存在が花のように現れている」なのであり、存在というものはそれぞれの現れによって在るのだと言う。
では存在しないとはどういうことかというと、これは「真空」という存在によって確かであると。そしてこれらの「存在する/存在しない」が「在る」の概念に則ったものであれば、それらを包括する上位概念が必要となる。それが「空」なのだ、と。
私は、私というものを究極に掘った先に在るものはありありとした明瞭な「空」だと感じている。私を構成する核が「空」だとして、その私が存在することを包むものもまた「空」なのだとすると、私たちは「空」を包み包まれている、という同時性の内、もしくは境に生を見出しているのではないかという気がしてくる。
ただそこにある。それだけで良いとされるのなら何と素晴らしいことか。
拡張的古典事実–
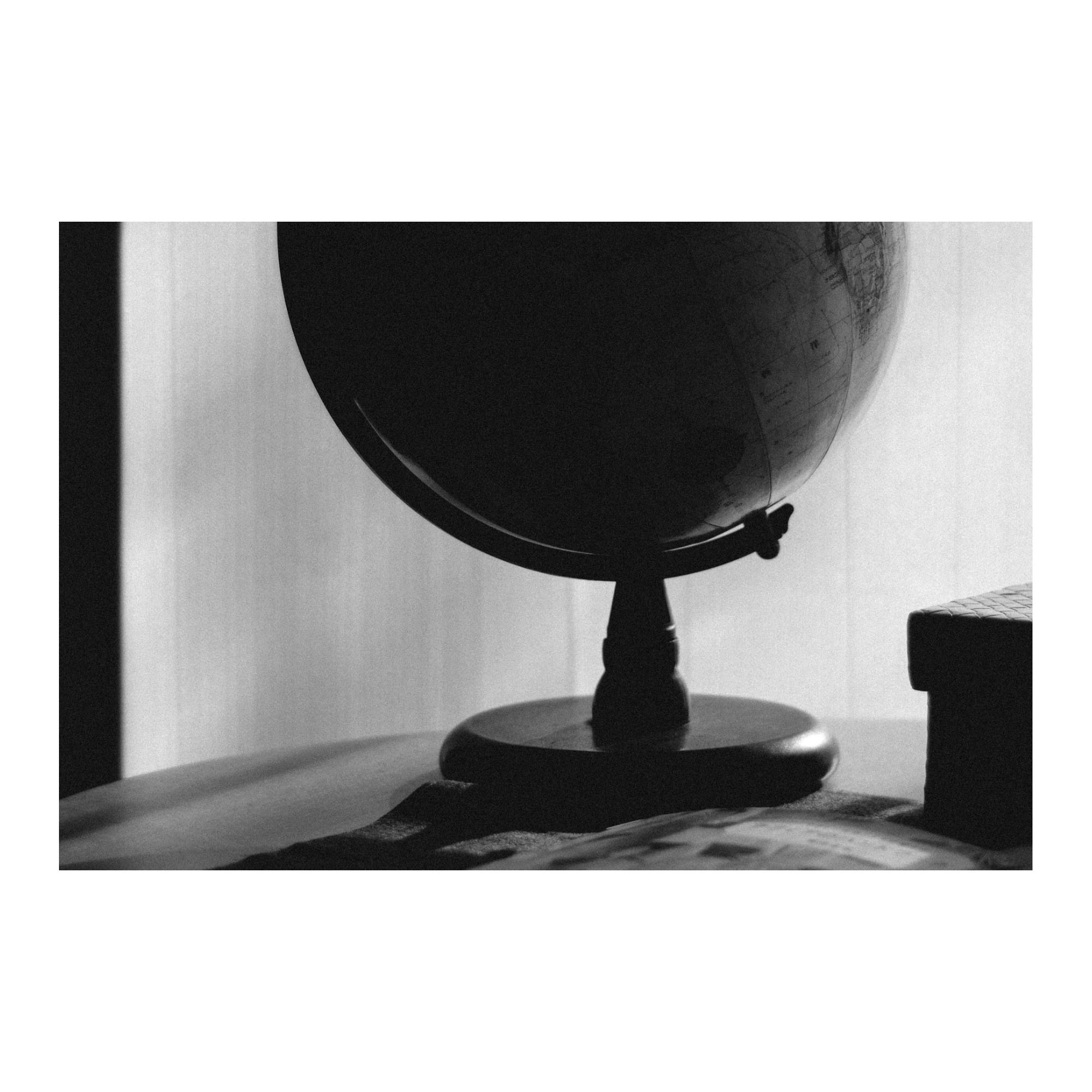
近年の創造的な新しい概念を創世記や神話、古事記などの古典に出自を求める動きが時々ある。つまり最近のこの考え方はすでにこれこれに載っていたよ、と拡大解釈することである。
上記の神話は往々にして抽象的な事象の連なりであり解釈の幅がある。それを利用して、さも近年の新しいイデオロギーがそれらの神話によって予測されていた、もしくは発端だと主張するのは閉鎖的な宗教擁護者がよく行う手法である。
こうやって後付けで物事を過剰に接続し神格化させることは真の創造的行為ではない。ましてや現実のテクノロジーの拡張性や生物学的進歩の倫理性について何も解決しないどころか問題をややこしくする。
現実主義者と合理性、及び理性で物事を思考しない人間との溝は、今後より一層深まっていくだろう。
生きる意味–
生きる意味はあるのかという議論をよく見る。
「種の保存のため」という人がいる。しかしそうであればもっと単純な細胞で良いはずである。「幸福になるため」という人がいる。しかしそうであれば苦しみや悲しみをもたらさない脳に直接作用する薬などを打てば良いはずである。
生きる意味は誰にも定められていない。だから自分で定めることができる。ハイデガーは「存在と時間」で本来的な生き方と非本来的な生き方を明らかにした。
私達は「意味を問うのではない、意味を問われているのだ」。この意識で生き方はより本来的な方向へ向かうだろう。
放つ–

近頃「中央を空白にしておく」ということを意識している。
例えば、
他人は分かり得ず、どのようにも転ぶものだとする、
そこには意味はなくただ事実がある、
作り得ないということから作り始める、
など。
人は力んだ状態より、常にニュートラルでいたほうが柔軟に対応できる。細部まで決め切らず、その状態を認めて放っておくことも大事だと思っている。
